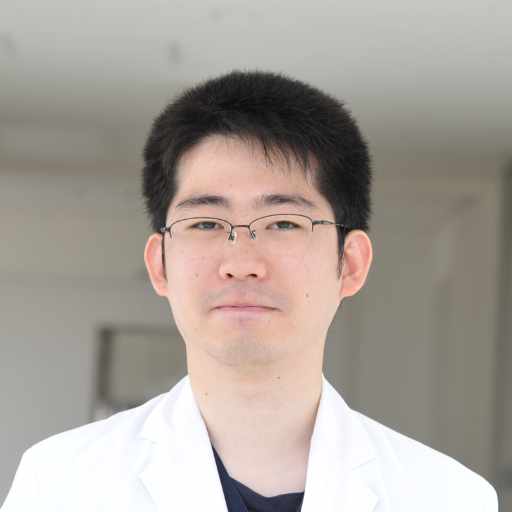
内田 待望 2025年入局
- 出身大学:
- 福井大学
- 初期研修先:
- 高山赤十字病院
- 当教室に入局した理由:
- 学生実習で神経内科の先生にお世話になったことがきっかけです。時に複雑な訴えから謎を解いていき診断をつけることに心惹かれました。初期研修は県外で行いましたが、縁あって福井に戻ってくることになりました。
- 入局を考えている研修医に一言:
- 日々何か不思議なことを探し、常に新しいことを勉強していきたいと思っています。一緒にいろいろなことを学んでいきましょう。
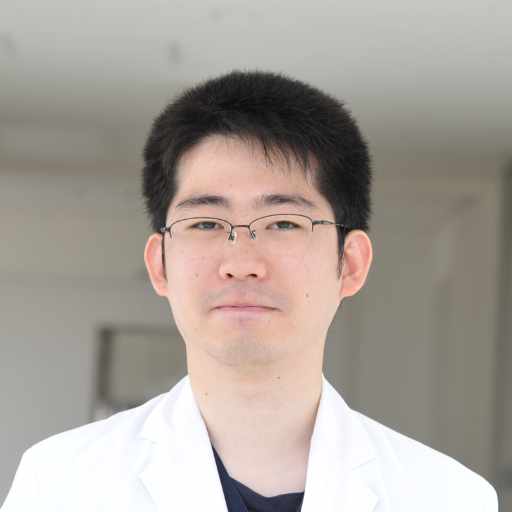
内田 待望 2025年入局

江口 茉優 2025年入局

臼井 宏二郎 2022年入局

山口 智久 2014年入局
脳神経内科領域の疾患は、脳卒中、神経免疫、認知症、変性疾患等の多岐に渡り、それぞれに専門性の高い医療を実践すること、また特に神経変性疾患では、患者さんの呼吸・栄養・運動・コミュニケーションなど、生きることにおける根源的な課題に対して最適なサポートを行うことを目指しています。
指導医・専門医として、若手の先生たちが幅広く学び・実践できるように、マンツーマンで指導を行うのはもちろんですが、研修医・若手だからこそ出てくるアイデアをできるだけ尊重し、自分も楽しく学るよう心掛けております。 そして当院の脳神経内科では、患者さん一人一人の診断・治療方針を決めるため、科長を含めた全員で顔を合わせて日々ディスカッションしています。チームワークを感じながら働くことができる点が大きな魅力と思います。ぜひ見学にいらしてください。

遠藤 芳徳 2011年入局
脳神経内科では脳梗塞や髄膜炎など入院時点で診断がわかっている病気だけではなく、他病院で診断がつかなかった患者さんの精査入院を行うことがあります。研修医でも積極的に鑑別診断を上げていただき、診療に参加することができます。カンファレンスや症例検討会で各症例について深く学ぶことができます。
また、技術的な面ではルンバールは何度か見学していただいた後は指導医の指導のもと研修医の先生に実際に行っていただくともあります。そのほかにもエコーが病棟にあるため頸部エコーを行う機会もあります。ルンバールや頸部エコーは行えるようになると救急外来で強い武器になると思います。

北﨑 佑樹 2014年入局
2014年度に脳神経内科へ入局した北﨑佑樹と申します。西山康裕教授ならびに医局の先生方のご厚意により、2025年4月から新潟大学脳研究所 統合脳機能研究センターに国内留学をさせていただいております。島田斉教授のご指導のもとで、脳の“ゴミ捨て場”と呼ばれる排出機能を画像で可視化し、アルツハイマー病など神経難病の発症・進行リスクを定量化する研究に挑戦しております。
研究面では、毎日画像解析に打ち込み、同じ分野の研究者と議論を重ねながら研鑽を積んでいます。臨床面でも、毎週の新潟大学 脳神経内科の症例検討会や回診に参加し、現場での学びを続けています。


国内留学の良さは、衣食住に大きな変化がないことです。家族は新しい街(とくに新潟市水族館)や食文化(日本酒!)を楽しみ、私も安心して研究に集中できています。趣味のプロバスケットボール観戦も、今年は家族みんなで新潟のチームを応援してしまっています。
また、福井大学の医局の先輩方が広く知られているおかげで、「福井大学の医局員」という立場による信頼をいただけております。著名な先生方とのご縁はもちろん、今後ともに研究を進める若手研究者との出会いが大きな刺激となっております。得た知見や経験を教室へ持ち帰り、若い先生方と共有して、教室全体の力をさらに高めたいと考えております。